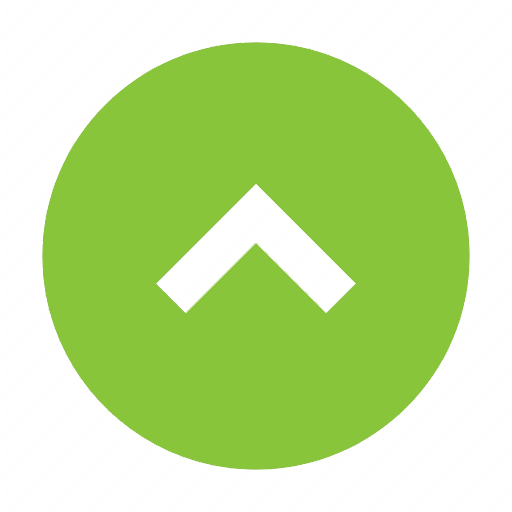先週の金曜日の朝のことです。みんなの登園を門で待っていた私は、Rちゃんとお父さんの姿に気付き早めに門を開けて二人を待っていました。ゆっくりと歩きながらこちらに向かっていたRちゃんのお父さんが途中でふと足をとめ上の方を見て耳を澄ましておられました。私の顔を見て、私の自宅の巣箱を指さし「鳴き声が聞こえますよ。」と教えてくださいました。ここ数週間は、お天気も悪く、週末は私も家の田んぼの田植えが忙しくて全く気づきませんでした。家に戻りしばらくみていると、本当に可愛い雛の鳴き声が聞こえます。そして、長い事待っていたらようやく巣箱から黒と白の可愛いシジュウカラの親鳥が餌をさがしに出ていきました。
この巣箱は、シジュウカラが入れる巣穴のサイズにして、3月の終わりにおひさまえんと私の自宅の二か所に設置したものでした。(シジュウカラの縄張りは100mくらいあるので、どちらかに入ればいいかなと思っていました。)4月頃はシジュウカラの鳴き声はするけれど、なかなか入ってくれなくて、今年はダメかなあと諦めていました。

シジュウカラは、白いほっぺたに黒いネクタイのような模様が特徴の小さい小鳥です。鳴き声はいろいろありますが、主に「ツィピーツィピーツィピー」がわかりやすいです。雛は孵化してから16日~19日で巣立つそうなので皆さんも登園するときにちょっと立ち止まって見てくださいね。
そしてきっと誰でも忙しい朝の時間に、時間の許す限り、Rちゃんとの登園をゆっくり楽しんで下さるRちゃんのお父さん、本当に素敵です。気づいてくださって、教えてくださってありがとうございます。
◇懇談会の予定
7月の許斐先生の懇談会は、7月10日(木)に宮司自治公民館で行われます。時間は、13時20分~14時50分です。許斐先生は先月から体調を崩されて、6月の懇談会はお休みでした。今月もし変更がありましたら、門に掲示いたしますので気を付けて見てください。よろしくお願いいたします。
なお、懇談会当日保育日でない方も、お子さまをお預かりできますので是非参加してください。『おひさま懇談会へようこそ』をご持参ください。
◇夏休みの日程
8月12日(火)~15日(金)です。
◇帽子を忘れずに持ってきてください。
あっという間に梅雨が明け、暑い夏の到来です。ご存じのように、子どもたちが気持ちよく外で過ごせるように園庭に遮光ネットを張っておりますが、今の日差しはとても強く気温も高いため、遮光ネットでも熱中症になりかねません。園では、毎日とにかく外に出るときは帽子を必ず被ること、そして、10分~15分経過したらお茶を飲みに戻るように子どもたちに声をかけています。キュウリもオクラもなり始め、先週から塩きゅうりと塩おくらを食べました。子どもたちは私達大人より身体も小さく地面からの距離が近いので、地面の温度や照り返しを一番に受けやすいです。園の帽子を一時置いていましたが、毎日みんなはびっしょり汗をかくので、不衛生にならないように園の帽子を使うのではなく、自分の帽子を被るようにお願いしています。毎日リュックと帽子をセットで園に持ってくることを子どもたちに伝えています。どうかお家の方もご協力ください。そして、金曜日には必ず帽子を洗ってきてください。よろしくお願いします。
◇お読みください。
『シリーズ授業 実践の批評と創造 ⑩障害児教育 発達の壁をこえる』岩波書店より
・ただそばにいればいいというものではなくて、大人が学校と関係ない部分で心情的に悩んでいたりすると、それを背負って子どもと対面するわけで、そういうときは、そばにいる時間は長くても、子どもと対面していないんですね。こっち側でどうしようどうしようと考えているから、子どもを見ていても見ていない。子どもはそういうことがわかるから、スッとどっかに行ってしまう。 私たちも外側から見ていると、わかります。子どもにまず表情がないし、先生のことを頼っていない。そういう意味では、大人は、自分の悩みはあっても、子どもと対面したときは、子どもにとっての自分になろうと努力することによって、悩みをスッと忘れたりして救われますね。P115
・させようと思うとできないものが、子どもが要求することにちゃんと応えているとできるようになる。人間の発達は、そうなっているのではないでしょうか。
長くかかるか短いかは別な問題として、子どもの要求する通り動いているのが一番です。子どもの言う通りに動いていれば、その子なりの健全な発達は期待できると私は信じます。P117~118
・好きなものを熱心に通してやった体験がないと、集中力は育たない。P123
・私が、そういうことを越えなければ次に行かれない状況にきっといたんだろうなと思いますし、現場では年中そういうことはあるのね。子どもたちって、ものすごく大人を育てる人たちなんです。学校というスペース自体を、子どもが育つだけじゃなく、子どもも大人もお母さんも、そこに集まっている者同士が育ち合う場所だというふうに、意識的にしっかり捉えることが大事なんじゃないかと思います。P131