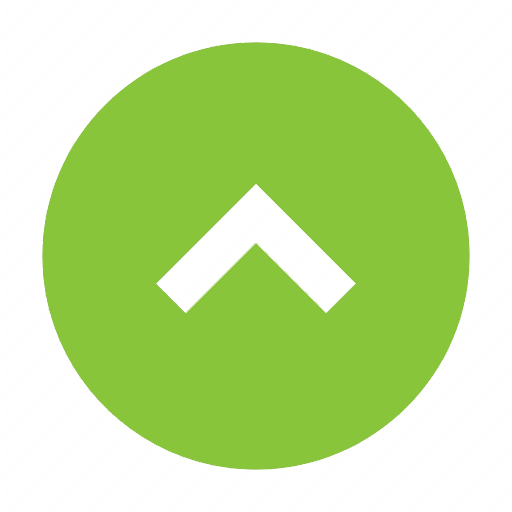大阪市立大空小学校は2006年に開校し、『みんなの学校』という映画になり話題を呼びました。先日大空小学校で9年間校長をされた木村泰子先生の講演を聴きました。講演会の副題は、【子どもの事実から人権を視点に インクルーシブ教育を問い直す~みんなの学校が教えてくれたこと~】およそ3時間半に及ぶ講演会でしたが、私の走り書きのメモをまとめてみました。
子どもの事実抜きにインクルーシブは語れません。目の前の子どもがすべての正解を持っているのが教育の場です。10年後の社会に子どもは大人になる。その時にちゃんとつかえる力を小1よりゲットしていく。これが学校の本質です。
権利条約の条例ですべての子どもが守れるか。そこに生きているすべての子が自分にとって幸せになれる条例とは。
大人が語った人権はスマホにかかれていました。
子どもが自分の言葉で語った人権は【空気】です。人権は空気です。不規則発言がどれほど大切か。空気がなかったら死んでしまうよ。環境。学校の全体の空気を安心して吸える。人にあわさなくていいという空気。
子どもと大人が社会を作っている。子どもは1人で働けない。大人が食べさせてくれるから生きている。聞き分けのよい「はい。頑張ります。」ではなくて、「嫌や!しんどいねん。頑張りたくない!」これを聞いてくれる大人が1人でもいたら、子どもは死なない。
2024年自殺者 527人 うち小学生15人 中学生163人 高校生349人
前の学校と大空小学校何が違う?
空気が違う。
息ができる学校。
無理せんと息ができる学校。当たり前に学ぶ地域の学校
今までの学校は、勝手にしゃべるな。勝手に動くな。勝手に逃げるな。
私たちがバトンタッチする子どもは、どんなこどもが育ってほしいか。
社会に迷惑かけないように、自分のことは自分でできるように、自立 ではなく【自律】 自分で考えて行動する。失敗してやり直す。
支援の介助の仕方が違う。大人がわかっていないだけ。
無理して来んでいいよ。ではなく
無理せんでも来れる学校をつくろう!
これが結果としてインクルーシブ。
どんな社会を作りたいの?
子ども同士の関係性の中で学び合う、育ちあう。障害を無きものにするのではなく
今こいつ困ってる。困らないようにするのが俺らの役目。
子どもと子どもを繋ぐことが私たち大人の仕事
「受け入れる」と言う言葉は排除に繋がる言葉。
この言葉がある間は、対等にはならない。
先生の熱心な指導が暴力に変わる。子どもが困った時に子どもが助けてといえる環境。子どもが言える環境。
殴った子に大丈夫?と言う言葉に変える。殴った子は困っている。今までは、叩かれた子に大丈夫?だった。殴った子には、殴るな謝れ!の指導。
こいつは悪い奴だ。周りがそう思わせる空気は指導が作っている。
当たり前を取り戻すのがインクルーシブ教育。
子ども同士でもお前、何殴ってるの?困ってるの?どうした?
トラブルを生きた学びにする。いじめではなく。
みんなの学校は素晴らしい。大空はすばらしい。と言われます。これを普通にしましょう。素晴らしいというと、特別になってしまう。
このすべての子どもたちに、人を大切にする力・チャレンジする力・表現できる力・考える力 この4つの力を育てていきたいです。
さあ、私たちのおひさまえんではどうでしょうか?
私たちは、毎日の生活の中で「絶対」と言うことはないと思います。
例えばみんなで何かをする時、みんなで一緒にできたらいいなあと思うけれど、まずはその子の今の気持ちを探りながら感じながら様子を見ています。そのうち子どもの方が自分から動きだして一緒にするときもあったり、その後の遊びの中でお友達と一緒に過ごす姿が見られたりします。もちろん、ずっと1人でいることもあります。そんな時は、黙ってその子の傍に座って過ごしてみます。また、自分の思いを貫きたくてお友達と喧嘩になってしまうこともあります。はたからみればわがままな言動であっても、その子が今感じているその思いにどう向き合ったらよいか。ただ、我慢させることや譲ることを教えるのではなく、その子の混沌とした気持ちをどう解きほぐせるか、本当に難しいです。でも、その子のことを私たち大人の言葉で決めつけてしまわないように、必死に考え向き合います。子どもから出るどんな姿も愛おしく大切な姿です。
そして、子どもたちからいろいろな要求ややりたいことが出てきたときは、どの子も臆することなく声にしてほしいですし、声をかけられた大人はすぐに「いいよ。しようね!」と言える大人でありたいと思います。私たち大人は、子どもたちが遊びに向き合い、楽しみ、夢中になっている姿を守り、遊びを通してみんなの思いを叶えるために協力を惜しまない、そんな思いで日々子どもたちと向きあって過ごしています。
木村先生の講演会を聴いて、私たち大人の何気ない子どもへの言葉が「空気」を汚してしまっているのではないかと感じました。日々の子どもたちへの声かけや大人の感じる心が自分中心の思いで発せられていないか。何よりも、子どもが主体であることを大切に、忘れないで子どもたちと関わっていきたいと思っています。
おひさまえんでは、『ここでは子ども一人一人が主役です』
◇懇談会の予定
9月の許斐先生の懇談会は、9月25日(木)に宮司自治公民館で行われます。時間は、13時20分~14時50分です。許斐先生は6月から体調を崩され入院されていましたが、無事に退院されました。ただ、まだ痛みが伴う毎日のようです。
懇談会当日保育日でない方も、お子さまをお預かりできますので是非参加してください。『おひさま懇談会へようこそ』をご持参ください。
◇ご覧になりましたか?
今月の福津市の広報に、可愛い男性3人の写真が表紙になっています。ご存じの方もおられるかもしれませんが、なんとこの3人の男性。皆さん、おひさまえんにお子さまを通わせてくださり卒園させて下さったお父様たちなのです。Sちゃん(11歳)、Jくん(7歳)そしてまだ在園生のRちゃんのお父さん。Tちゃん(12歳)のお父さん。そして、Kくん(10歳)、Mちゃん(8歳)のお父さんです。おひさまえんに子どもたちが通っているころから、そして今もとっても仲良しで本当に素敵な心持ちの方々です。広報誌を見た瞬間、あらっ!なんて可愛い!と思いました。そしてとても嬉しい気持ちになりました。
お父さんだけでなく、おひさまえんの卒園生のお母さん達も今でも仲良く集ってある方々もおられます。次回は、そのお母さん達をご紹介します。
子どもを通じて、知り合い、同じ子育て感を持って、互いを尊重しながら過ごされて本当に素敵だなと嬉しい気持ちでいっぱいです。

https://www.city.fukutsu.lg.jp/material/files/group/1/2509tamanoi.pdf